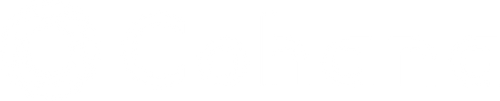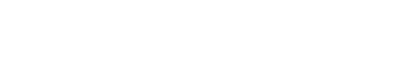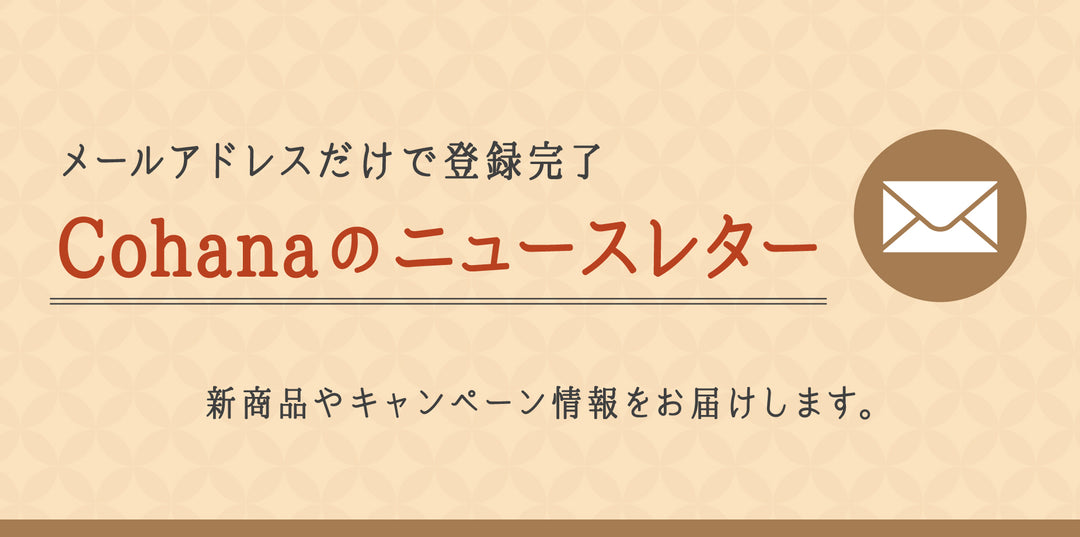Cohana 基本の5色の物語 ふかがわねず

日本人は四季の移り変わりの中で様々な色を感覚で感じ取り、名前を付け、毎日の生活に取り込み楽しんできました。
日本の伝統色は460種類以上あるといわれており、日本人の色彩感覚の豊かさが感じられます。この数多く存在する日本の伝統色の中から、日本の良さが伝わる色展開にこだわり、Cohanaの基本の5色を選びました。
Cohanaの基本の5色から「ふかがわねず」についての Story と おすすめ商品 をおとどけします。

水色がかった明るい灰色。江戸時代の深川界隈のいなせな若衆や、渋さを好んだ芸子が愛した、日本人特有の美意識「粋」が感じられる洒落た色です。
「四十八茶百鼠(しじゅうはっちゃひゃくねずみ)」という言葉をご存じでしょうか?
江戸時代の庶民が生み出した茶色は48種類、鼠色は100種類も、たくさんあるという表現です。実際は茶色も鼠色も謳われているこの数以上の色彩が存在したそうです。
茶色や鼠色がこれだけたくさん生まれた背景には、江戸幕府が出した「奢侈禁止令(しゃしきんしれい)」という贅沢禁止令があります。
奢とは「おごりたかぶる」、侈とは「ほしいままにする」という意味で、身分不相応に衣装に贅を尽くす事が禁じられ、庶民の着物の色・柄・生地には厳しい規制がかけられました。

お構いなしの色として「茶」「鼠」「藍」のみが許された色となりました。
おしゃれをあきらめない庶民が、許された色の範囲でたくさんの色彩を追求した結果、膨大な種類の茶色や鼠色が生まれ、日本人の色の微妙な差を見分けて楽しむ感覚と美意識が磨かれたのです。
また、火事が多かった江戸時代「灰色」という表現は縁起が悪いと、火災を連想させない「鼠色」が色銘に使われたといいます。
華やかで明るい色が多い平安時代、はっきりとした色味が多いその後の鎌倉・室町・安土桃山時代と比較して、江戸時代の日本の伝統色はくすんだ渋めの色彩で溢れています。
その背景を知ると、江戸時代の人たちの生き方を反映した伝統色もまた素晴らしく、粋を感じずにはいられません。
ふかがわねずの道具がもたらすモードでシックな雰囲気が、あなたの手作りの時間に優しく寄り添います。ぜひこの色をコレクションに加えてみてください。「ふかがわねず」で統一されたお裁縫箱のコーディネートもおすすめです。